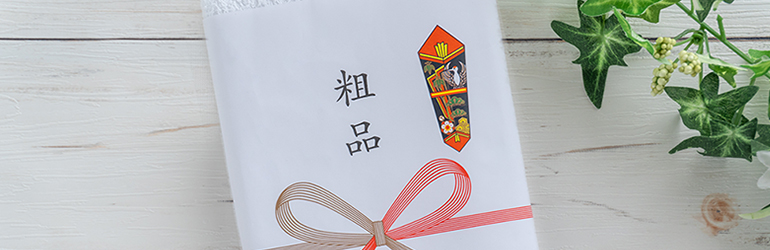「粗品」という言葉は、日本の伝統的な文化に根付いた表現であり、現代でもさまざまなシーンで使われています。本記事では記念品コラムとして、「粗品」とはどのようなものか、利用シーンやマナーについてもご紹介していきます。
「粗品」とは?
粗品とは、本来「粗末な品物」といった意味ですが、実際には謙遜の気持ちを込めて贈り物を指す言葉として使われます。
贈り物をする際に「これはたいしたものではありませんが…」という意味合いを持たせて、贈る側が控えめな態度を示すための言葉なのです。
この謙遜の姿勢は贈り物の価値を押し付けない日本特有の礼儀であると考えられています。
また、粗品は特別な意味を持たせない気軽な贈り物や、感謝の気持ちをさりげなく伝えるためのものです。
そのため贈る相手との関係性に応じて、あまり高価なものではなく、日常的に使えるものや、誰にでも喜ばれるような実用的なものが選ばれることが一般的です。
粗品とノベルティの違い
粗品とノベルティは、いずれも贈り物として使われる点では共通しています。しかし、その目的や贈る相手、場面において明確な違いがあります。
粗品は、主に感謝やご挨拶の気持ちを込めて、控えめに贈る品物です。
企業が取引先やお客様へお礼として渡す際などに活用されます。一方ノベルティは、企業やブランドの認知拡大・販促を目的に、不特定多数に配布する広告物の一種です。
名称やロゴが印刷された実用的なアイテムが多く、マーケティング施策として活用されています。
このように、粗品とノベルティは目的や位置づけが異なるため、使用シーンに応じた選定が求められます。
粗品の利用シーン

「粗品」は、日常のさまざまなシーンで活用されています。
取引先への訪問時
ビジネスシーンでは、取引先を訪問する際に「粗品」を持参することが一般的です。
これは相手の時間を割いてもらったことへの感謝や、今後の良好な関係を築くための手段として使われます。
粗品としては、会社のロゴ入りのタオルや文房具など、相手が気軽に使える日用品が選ばれることが多いです。
イベントやセミナーでの配布
企業・団体が開催するイベント・セミナーといったものでは、参加者への粗品としてロゴ入りの記念品・パンフレットとともに配布されることが多いです。
これには、参加してくれたことへの感謝の気持ちや、企業やサービスの印象を深めてもらう目的があります。配布される粗品は、ペン、メモ帳、エコバッグなどが一般的です。
冠婚葬祭での返礼品
結婚式や葬儀などの冠婚葬祭の場でも「粗品」は活用されます。結婚式では引き出物として粗品が用いられることがあり、葬儀では、会葬御礼として香典返しとは別に粗品を配布することがあります。
このような場面では、贈られる側の宗教的背景や嗜好を考慮し、相手が無理なく受け取れる品物を選ぶことが重要です。
季節の挨拶やお礼の品
季節の挨拶として、夏や年末に「粗品」を贈ることもあります。夏の「暑中見舞い」や冬の「年末のご挨拶」として、タオルや洗剤、食品などの実用的な品物が選ばれます。
また何かの手伝いをしてもらったり、協力を得た際のお礼として「粗品」を贈ったりすることもあります。このような場合も高価すぎないものか、感謝の気持ちを伝えられるものが選ばれることが多いです。
粗品に関する注意点
粗品は一般的なプレゼントよりも、フォーマルなシーンで渡されることが多いです。
こちらでは、粗品に関する注意点をご紹介します。
粗品を渡す際のマナーについて
「粗品」を渡す際にはいくつかのマナーを守ることが大切です。以下に、その基本的なマナーを紹介します。
言葉遣い
「粗品」を渡す際の言葉遣いも重要です。基本的には「これは粗品ですが、どうぞお受け取りください」といった謙遜の言葉を添えるのが一般的です。言葉遣いに気を配ることで、相手に対する敬意や感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。
品物の選び方
「粗品」を選ぶ際には、相手の立場や状況を考慮した品物を選ぶことが大切です。贈り物が高価すぎると、相手に負担をかけることになりかねません。また相手が使いやすい実用的なものや、季節感を取り入れた品物を選ぶとなお良いでしょう。
粗品を選ぶ際のマナー
粗品は、感謝やご挨拶の気持ちを表すための贈り物であるため、選定には細やかな配慮が求められます。相手の立場や贈る場面にふさわしい品物を選ぶことが大切です。
実用性や季節感のあるものは好印象を与えやすく、ビジネスシーンでは派手すぎない落ち着いたデザインが適しています。
また、名入れやブランドロゴ入りの場合は、主張が強すぎないこともポイントです。
熨斗の使い方や価格帯もマナーの一部であるため、細部まで気を配りましょう。
熨斗の表記と使い方
粗品に熨斗を添える場合は、目的に応じた表書きを選びます。企業間のご挨拶や販促品では、「粗品」や「ご挨拶」が一般的です。
個人向けでは「御礼」「記念品」など、場面にふさわしい文言を選びましょう。
表書きは水引の上に記載し、下段には会社名や個人名を記します。ビジネスで配布する場合には社名を記載するのが慣例です。
水引は紅白の蝶結びが基本とされ、何度あってもよい慶事や日常的な贈り物に適しています。
用途に応じた正しい熨斗の使い方は、相手への心配りの表れとなります。
粗品の価格相場
粗品の価格帯は、贈る相手や目的によって異なります。
一般的なビジネスシーンでは、1個あたり100円~500円程度の実用品が選ばれる傾向にあります。訪問時の手土産や展示会での配布品などは、コストを抑えつつも印象に残るアイテムが重視されます。冠婚葬祭や個人の感謝を示す場では、1,000円前後のギフトセットが選ばれることもあります。
高価すぎる粗品は、相手に気を遣わせてしまう可能性があるため注意が必要です。
贈り物は気持ちが伝わることが第一であり、価格よりも配慮や誠意が重視されます。
粗品の活用シーン

粗品は場面に応じた使い分けによって、その効果や印象が大きく変わります。こちらでは、法人向けと個人向けに分けて具体的な活用シーンをご紹介します。
法人向け・ビジネスシーン
法人における粗品は、企業活動の一環として活用されます。たとえば、展示会・セミナーの来場者配布、取引先への訪問時、年末年始のご挨拶などが代表例です。
名入れグッズや実用性のあるアイテムは、企業イメージの向上や関係構築に効果的です。
控えめながらも心配りが伝わる粗品は、信頼関係の強化につながります。
個人向け・日常シーン
個人で粗品を用いる場面には、近所付き合いや趣味の集まり、お祝い返しなどがあります。気取らず渡せる小さな贈り物は、感謝や思いやりの気持ちを自然に伝える手段です。
季節の挨拶やちょっとした返礼品としても重宝され、日常の人間関係を円滑にする効果があります。
相手の好みや生活スタイルを配慮した選定がポイントです。
おわりに
本記事では、「粗品」とは何か、その意味や活用シーン、マナーについて解説しました。粗品は、ビジネス・日常問わず感謝を形にする有効な手段です。
場面や相手に応じた適切な品選びと丁寧な対応は、信頼構築に直結します。
企業や個人での贈答に粗品を上手く取り入れ、円滑な関係づくりに役立ててみてください。
記念品関連
能作・錫製記念品

より能(よ)い鋳物を、より能(よ)く作る
株式会社 能作は大正5年(1916年)創業
富山県、高岡銅器の伝統を受け継ぐ鋳物メーカーです。
伝統的な仏具、茶道具、花器などをはじめ、近年では高岡銅器の鋳造・加工技術を応用し、テーブルウェア、インテリア雑貨、建築金物や医療機器などのあたらしい分野にも挑戦しています。先人の技術を継承し、素材を最大限に生かすデザインを探求し続け、高岡の地で人に愛され 地域に誇れるものづくりを目指しています。

「能作」記念品 商品一覧
セミオーダー・オリジナル記念品
アワードやプライズとして人気の高いセミオーダー記念品。記念品本体に加工を施すオリジナルデザインでお一つからオーダーが可能です。デザイン性にも優れた美しいガラス製の記念品、贈り物として選ばれることの多い時計付き記念楯(盾)やペーパーウェイト等の記念品などを取り扱っております。

セミオーダー・オリジナル商品一覧
社内表彰記念品
会社に貢献してきた事に対して功績を讃える社内表彰。モチベーションアップに関わる大切な表彰式には記念になる表彰クッズを用意したいものです。
豊富な記念品の品揃えの中から、従業員様向けの記念品から贈答品やギフトをご予算や用途に合わせて表彰記念品専門店がご提案いたします。

社内表彰記念品一覧